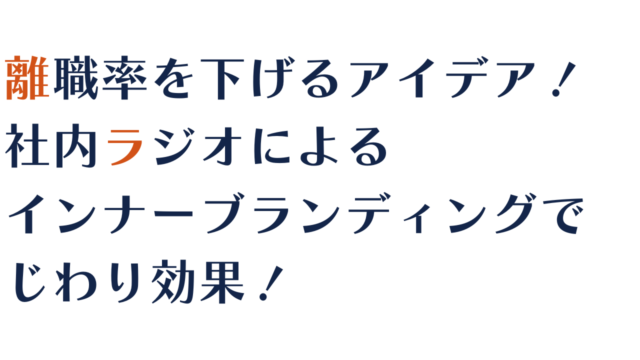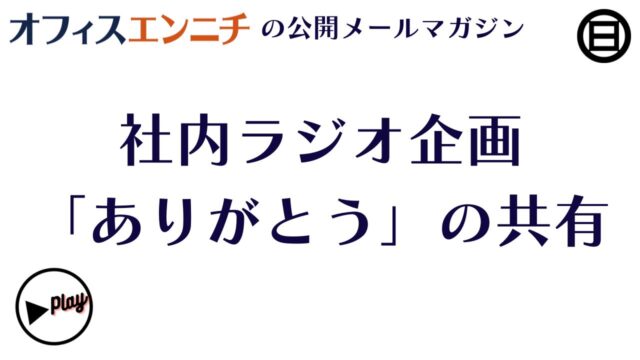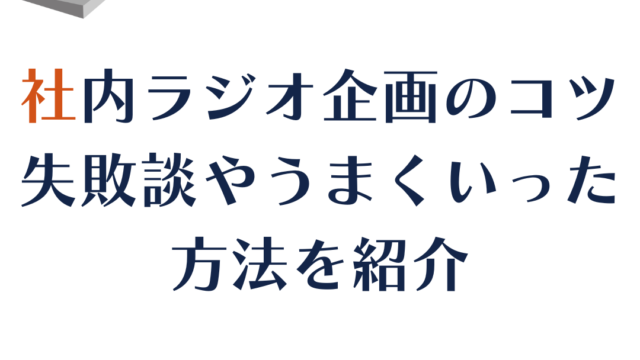社内ラジオをはじめたい企業様、始めたいけど話せるのだろうか、というモヤモヤした困りにズバリ答える記事です。
社内ラジオDJを社内で行うには、どのような社員が適任か。また、話し方、聞き方のコツはどうなんだ?体制は?
社内ラジオ事業者として日本初であり、ナンバーワンの実績を誇る株式会社オフィスエンニチの高間がお伝えいたします。
Contents
社内ラジオのDJの選び方の3つのポイント
社内で好かれている社員が行うのが最もよいです。これは最も重要な要素。ラジオが聞かれる上でのアドバンテージになります。(ちなみにこちらはわたしの私見です)それを踏まえ3つ挙げてみました。
要素を3点
- 人気がある
- 聞き上手
- できれば2人体制
人気がある社員(好かれやすい社員)

人気というと下世話に聞こえるならば、人望のある人柄ということでしょうか。ラジオは人柄のメディア。社内で好かれている、人望のある社員の人柄を勘案して決めてくださいませ。
ちなみに、話し上手である、という要素は必須ではありません。わたしがポッドキャストで頻繁に聞いている番組のDJさんはプロのラジオDJではありません。
私が好きな番組はいくつかあるのですが、共通しているのは内容を作るための努力をしているということです。
素人の目的のないフリートーク(ダベリ)は聞くに堪えませんが、面白い番組はコンテンツが濃いので、ニーズにさされば、あまり話し上手でなくても気になりません。話し上手、や滑舌がよい、など話すためのスキルは番組運営のポイントの4番目くらいでしょうか?
聞き上手であること

これは大事な要素です。相手より、自分が話したい社内ラジオDJでは、その社員さんの発信する番組になってしまい、社内ラジオの継続が難しいでしょう。
異動などで、他の社員がDJを交代しづらくなります。社内で行うラジオはインタビューが主体になります。インタビュー上手な社員さんがよいてす。聞き方のコツは後述致します。
できれば2人体制

これは運営する上で心強いポイントです。2人いれば、ゲストインタビュー時にトークに詰まった時に焦らなくてすみます。できれば、男女ペアなど、性別に偏りがない体制がよいです。
では、DJを選んだら、次に話し方!と行きたいところですが、まずは話し方より重要な聞き方についてお話します。
社内ラジオDJの聞き方の3つのポイント
話し方よりも大事な力は実は聞き方なんです。インタビュー時には相手の話を上手く引き出すことがテクニックです。態度や、質問の仕方については別のページでお話します。ポイントは3つです。
- うなずき
- 相槌(あいづち)
- 繰り返し
うなずき

とても簡単です。首を縦に振るだけです。しかしラジオでは動きが伝わりませんので、首を縦振りながらええ、うん、うんとか何か言葉発することでリスナーに届きます。
相槌(あいづち)
こちらも簡単です。相手の話のわずかな切れ目に、はい、ええ、なるほど、などの短い言葉を差し込むだけです。具体的な言葉としては・・
「はい」
「へー」
「うん」
「ええ」
「わかる」
「なるほど」
「本当」
などがあります。
この相槌の効果は大きいです。相手が話している時に聞き手の相槌がない場合、話し手は不安になります。相槌には不安を払拭し、もっと話したいという気持ちにさせる効果があります。
下のリンクは参考資料です。実際に社内のラジオ番組で行ったものをサンプルとして用意致しました。
この回では、部門のリーダーに、どんな仕事をしているのか、聞いているのですが、うなずき、相槌、繰り返しを使っています。また、質問で掘り下げることもしてます。
実際のあいづちの例
以下は2022年に制作した株式会社リゲッタ様でのラジオです。3分25秒くらいから、私は相づちだけで、ずっと聞いています。質問の仕方については、別の機会に書きたいと思います。
繰り返し
 繰り返しとは「オウムがえし」のことです
繰り返しとは「オウムがえし」のことです相手の言葉を繰り返す。ポイントは二つです。あなたの話を聞いています、という態度を表すテクニックです。
・相手の話のポイントとなりそうな単語をそのまま繰り返す
・語尾を下げる
これにより、話し手にドライブをかける効果が出ます。繰り返すポイントは以下です。
感情が発露した部分

感情の発露した部分は必ず捉えて繰り返しましょう。感情をトレースすることで、エピソードがイキイキとし始めます。
「会社に行くのが嫌なんです」
「嫌なんです」(語尾を下げる)
「嫌なんですよー」
「ちなみに、何がいやなんですかー?」
事実の部分
感情の発露と同じく重要そうな事実を繰り返します。
「〇〇社からの発注が突然止まることがあるんです」
「止まる」(語尾を下げる)
「そうなんです、突然止まるんですよ」
社内ラジオのDJのテクニックとして大事なのは相手にどんどん話してもらう事と、テンポよく進行すること。どのテクニックも難しくはないですが、やってみると、照れが先行してすぐにできないはずです。照れを押し切ってできるようになるには意識して練習するのみ。
さて、ここまで3つのポイントをみてきました。これらは実は「ペーシング」と呼ばれるテクニックです。マラソンのペースメイカーの「ペース」と同じ。
相手のペースにあわせる、というテクニックがペーシング。言語・非言語ともにありますが、この記事では、言語によるペーシングテクニックを解説いたしました。続いて、話し方の3つのポイントを解説いたします。
話し方の3つのポイント
さて、次に、話し方のポイントをまとめました。
- 台本を用意する
- 抑揚をつける
- 相手の話をまとめる
台本を用意する
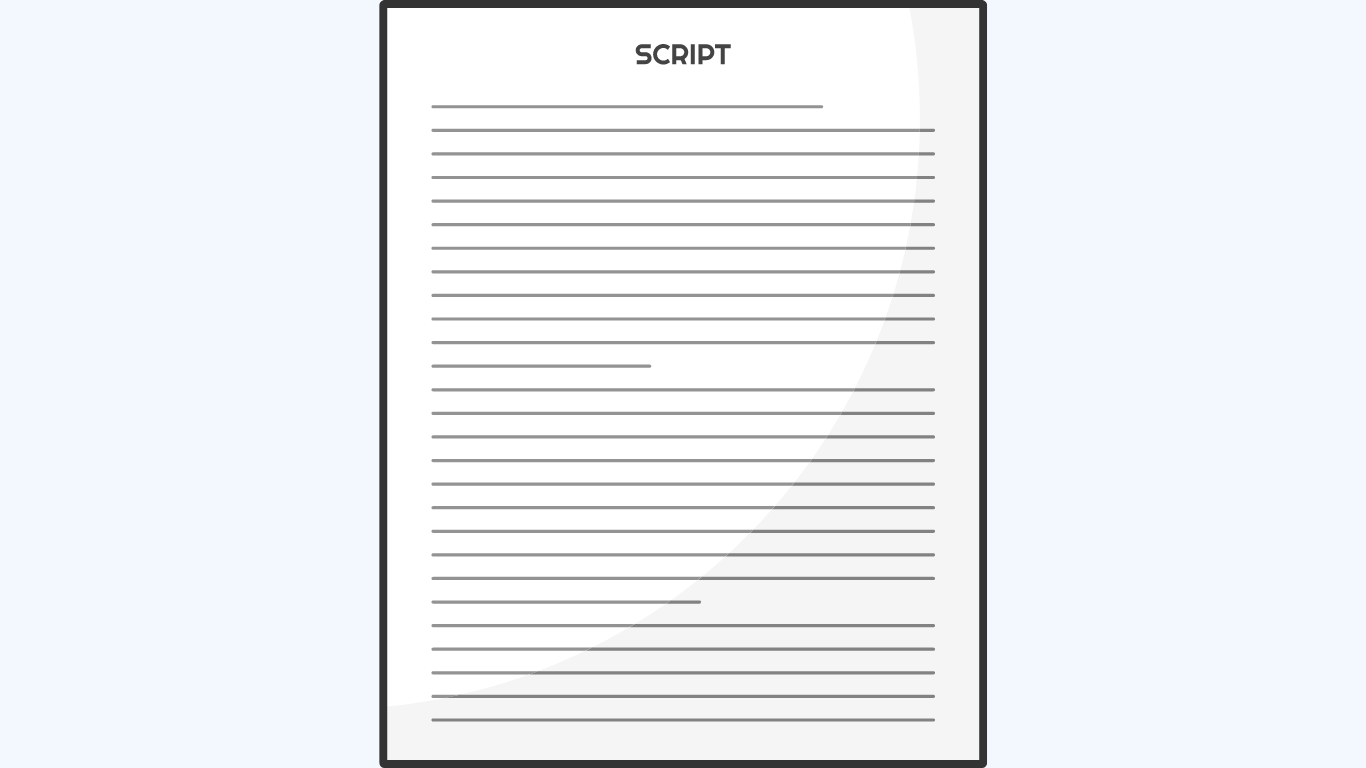
出演者+ゲストで行うなら台本は用意しましょう。オープニングの挨拶から、最後のセリフまで、一字一句全て書き起こすくらいの気持で。
社内ラジオはDJが話したいことを中心に発信することは多くは無いかもしれません(インタビューが多い)。ゲストは緊張することが多いです。台本がガイドになって安心感を与えます。また台本があると、DJの「えー」「あのー」が減ります。
不要な言葉が減る
「えー」
「あのー」
など、意味のない言葉を発してしまうのは、「何かいわなきゃ」と困っているときか、次に言う言葉を考えているときです。これは、極力出さないようにしたい癖です。
リスナーは話し手のどのような癖が気になるか、わかりません。癖でリスナーが離れてしまうともったいないです。型を崩すのはフリートークが十分にできるようになってからでも遅くありません。
抑揚をつける
話し手としての社内ラジオDJの役割はテンポよく展開をつくること。インタビューが主体となる社内ラジオでは、ゲストが常に話上手とは限りません。
ゲストの癖は聞きやすくも、聞きにくくもなります。社内ラジオのDJの役割はゲストの話をうまく引き出しながら、リスナーが最後まで番組を聞いていただきやすいように、うまく場面を切り替えること。
ゲストの話を、遮らないように、かつ面白い話や気づきを引き出しつつ行うのがコツ。私は社内ラジオDJとして落語家や講談師の話し方を参考にしています。
【抑揚】強弱をつける
【講談】神田伯山「中村仲蔵」in 浅草演芸ホール(2020年2月21日口演)
話し方に強弱をつけるのはとても有効な抑揚のテクニックです。
19分24秒くらいからをみてください。動画をクリックすると19分20秒くらいから始まります。社内ラジオは講談ではありませんから、芝居を打つ必要はありませんが、強弱をつけると、表現に幅が出て、一気にリスナーの注意を惹き付けることができます。
「ガラガラガラガラ(と、扉を)開けて入ってきた1人の男」
普通に読むとなんということのない文章ですが、表現力次第で迫力が出ますね。
だからおれは食いたくもねえ蕎麦とにらめっこしてんだ
役の工夫がつかねえ(悲壮な表情、声で大きく)
思っておりますところ
ガラガラガラガラ!(大きく、力強く)
(戸を)開けて入ってきた、1人の男
年の頃なら32,3でございましょうか、浪人体だ
「ガラガラガラガラ!」と蕎麦屋に入ってきた「一人の浪人が入ってきた」映像が眼の前に浮かぶようです。
ラジオでの例
感情を語る部分を強調すると、とても伝わりやすいです。下はゲストスピーカーが話している例ですが、強調すべきポイントを力強く意識してみました。
自社のECサイトに、写真をそのまま載せるんじゃなくて、しっかりと画像の補正をしてからページに載っけるんです。
お客さんの手元に届いた時にページに載ってる色味と手元に届いた実際の商品の色味が乖離がないようにしておかないと
「あー、思っていたのと違うわ」(すこし小さくゆっくり、残念そうな声で)
という残念体験みたいなことになっちゃうので、 その辺はしっかりとやっています。
しかし、この作業が実に大変で(つよくゆっくりと)
いかがでしょう。画像補正の作業がとても大変だ、という気持ちがよく伝わります。
【抑揚】間を恐れない
社内ラジオは沈黙してもOKです。間を恐れず、むしろ効果的に使いましょう。心のなかで良いので、次の2つのパターンを読んでみてください。
パターン1(間を意識しない)
おもっておりますところ、ガラガラガラガラ!と開けて入ってきた、1人の男
パターン2
だからおれは食いたくもねえ蕎麦とにらめっこしてんだ
間0.5秒
役の工夫がつかねえ(悲壮な表情、声で大きく)
思っておりますところ
ガラガラガラガラ!(大きく、力強く)
間1秒
(戸を)開けて入ってきた、1人の男
年の頃なら32,3でございましょうか、浪人体だ
いかがでしょうか。間をあけるだけでも、注意を惹く話し方になることがわかると思います。間はリスナーの注意を一瞬で惹き付ける、表現手段です。講談師のような話し方をする社内DJはいませんが、テクニックとしての「間」という表現手段があるということを知っていただくと良いです。
【抑揚】高低をつける
社内ラジオDJはリスナーを惹き付ける能力が求められます。導入部分などは声を高めに元気よく、テンポよく。社内ラジオはゲストを呼んでインタビュートークすることがほとんど。高い声を出すと元気な印象になります。

ゲストは社内ラジオでも緊張します。第一声を放つ、メインDJが心持ち高めの声、心持ち高めのテンションで滑り出すことによって、ゲストを心理的に誘導します。
ゲストとの間にラポールが形成されていると、ゲストはDJのトーンに合わせて話す心理状態になります。
その他のテクニック
相手の話をまとめる
社内ラジオのDJは自分がどんどん話すより、聞き出すことが大事。話し上手というより、相手の話を聞いて「それってこういうことですかね?」と相手の話を短く要約することがポイントとなります。
先程も紹介した実際に配信したラジオ番組です。5分くらいから、聞き取ったコトを「こんな感じで理解したんですが、あってますか」とわかったことを返しています。
わかったフリをしない
また、わかったふりをしないで、よくわからないところはよくわからないと言いましょう。
「わかりません」
とストレートに言うのも良いですし、
「私はこんな理解をしたんですが、あってますか?」などでも良いです。上記の番組内の3分25秒くらいで「わかりません!」と実際に言っています。
ちなみに、あなたが分かっていない部分はリスナーもわかっていないです。理解していない、ということを惜しげもなくさらけ出すと、リスナーは安心します。むしろ、相手の話すことを、よく分かっていないほうが良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょか?社内ラジオを始めたい、DJの選び方や話し方、聞き方の3つのポイントを網羅しました。
当記事で書いた事をできるようになると確実にいろいろな社員の話を聞け、引き出せる社内ラジオDJを育てることができます。
記事だけでは難しい、というあなた。当社は研修メニューもございますのでお気軽に↓